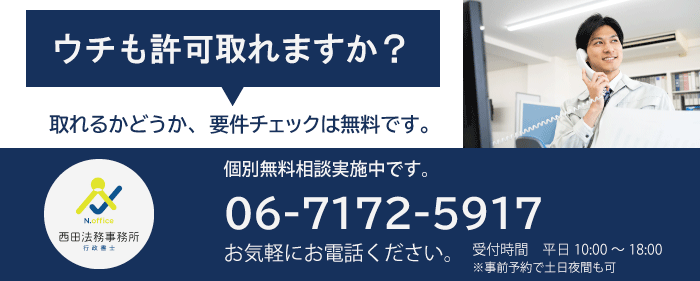解体工事業に必要な許可とは
住宅やビルの老朽化に伴い、解体工事の需要は年々増えています。
解体工事を新しく始めようと考える建設業者も多いのですが、解体工事には建設業法に基づく「解体工事業の許可」が必要です。
さらに、解体工事によって発生するコンクリートがらや木くずなどの廃棄物を自社で運搬したい場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可も取得しておかなければならない場合が多いです。
つまり、解体工事業の場合は、建設業許可(解体工事業)と産廃収集運搬業許可の両方が必要になるケースが多いのです。
両方の許可で業績アップを狙う
解体工事業の許可に加えて産廃収集運搬業の許可も備えれば、工事から廃棄物処分までを自社で完結できる体制が整います。これは元請や施主から見れば大きな安心材料となり、「解体から処分までワンストップで任せられる会社」として信頼を得やすくなります。
さらに、仕事の流れを一貫して管理できるため、外注コストを抑えて利益率を高めることもできます。近年は環境への配慮や適正処理の徹底が社会的にも強く求められており、許可を両方そろえていること自体が競争力の証明になります。
この記事では、この二つの許可をどう組み合わせて準備すべきかをわかりやすく解説します。
まずは「解体工事業」の許可を取る
解体工事を500万円以上の規模で請け負うには、建設業法に基づく「解体工事業」の許可が必須です。平成28年からは独立した業種として明確に位置づけられており、「とび・土工工事業」では代替できなくなっています。
許可を受けるには、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基盤、社会保険加入状況などの要件をクリアすることが必要です。
特に専任技術者は、解体に関する国家資格や一定年数の実務経験が必要です。
資格を持つ人材を確保するか、実務経験を裏づける契約書・注文書などの資料をきちんと整備しておくことがポイントです。
解体工事をするなら「産廃収集運搬業許可」も欠かせない
解体工事を行えば必ず廃棄物が出ます。
コンクリートがら、金属くず、木材などはすべて産業廃棄物として扱われ、適切な処理が法律で義務づけられています。
もし廃棄物の運搬を他社に委託するなら、自社では解体工事業の許可だけで足ります。
しかし「工事から処分場までを一貫して自社で担いたい」「元請から処分まで任せたいと要望された」という場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
この許可は都道府県が管轄しており、運搬車両の確保、事務所要件、講習会の修了などが必須です。
特に講習会は、これを受講しなければ申請できません。
許可取得の流れと準備
1. 事業計画を整理する
まずは「どこまで自社で担うか」を明確にしましょう。
• 解体工事だけを行うのか
• 発生した廃棄物を運搬まで自社で行うのか
• 将来的に処分場も整備して対応するのか
計画の範囲によって、取るべき許可の組み合わせが変わります。
2. 解体工事業許可の準備
解体工事業の許可申請には次のような準備が必要です。
• 経営業務に関する経験者:経営業務の管理責任者になるために必要です。
• 専任技術者の確保:一級・二級建築施工管理技士や、または一定年数の解体工事の実務経験者が必要です。
• 財産要件:500万円以上の自己資本など、財産的基盤を証明する資料。
• 社会保険加入:健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況を整備していること。
申請書に添付する書類も多く、他には登記事項証明書、納税証明書、工事契約書、決算書などが必要となります。
3. 産廃収集運搬業許可の準備
解体工事に伴う廃棄物を運搬するなら、以下の準備が必須です。
• 講習会の受講:申請前に講習会を修了していることが必要です。
• 運搬車両の確保:廃棄物を適切に運搬できるダンプやトラック。
• 車両・容器の写真や車検証:申請時に添付。
• 事務所の要件:机・棚・固定電話など、営業実態があること。
産廃の許可は都道府県ごとに必要なので、複数エリアで事業を行う場合は、営業範囲に対応する都道府県ごとに申請が必要です。
4. スケジュールを逆算する
解体工事業の許可は申請から取得まで1~2か月かかるのが一般的です。
産廃業許可も講習会の日程や書類準備の関係で同程度の期間が必要です。
両方を同時に進めることも可能ですが、書類作成や資格確認などが重なるため、余裕を持った計画を立てるのが賢明です。「案件が決まってから急いで申請」では間に合わないため、早めの準備こそが成功のポイントです。
まとめ
解体工事を始めるには「解体工事業の許可」が必要であり、廃棄物の運搬を自社で行うなら「産業廃棄物収集運搬業許可」も欠かせません。
二つの許可はそれぞれ別制度ですが、組み合わせて備えることで、仕事の幅が広がり、顧客からの信頼度や利益率も向上します。
これから解体分野に参入する方は、まず自社の事業計画を整理し、解体工事業の許可を土台に据えたうえで、産廃収集運搬業の許可もあわせて準備することをおすすめします。
まずは無料相談で、あなたのケースを確認してみませんか?
許可申請には、要件のチェック・資料の整理など、一定の時間がかかります。
だからこそ、「これからどうすればいいか分からない」と思った段階で一度ご相談いただくことをおすすめしています。
丁寧にヒアリングすることで、
どこまで要件をクリアできているか
どんな書類を用意すればいいか
申請までにどんな準備が必要か
私たちは、こうした点を一緒に整理しながら、現実的な申請の見通しをご提示いたします。
許可が取れるか不安な方へ。
第一歩は、悩みを言葉にすることから
申請はまだ決めていないという方でも、無料相談は歓迎しております。
「もしかしたら自分にもできるかもしれない」
――そんな気づきが、相談の場で生まれることも多くあります。
建設業許可のこと、相談してみませんか?

「許可が必要って言われたけど、何から始めたらいいのか…」
「書類が多すぎて手が止まっている…」
そんなときは、一度ご相談ください。
大阪府・兵庫県の建設業許可に詳しい当事務所が、あなたの申請をしっかりサポートいたします。
よくあるご相談
建設業許可の申請には、意外と多くの落とし穴があります。
当事務所に寄せられるご相談の一例をご紹介します。
• 「資格がいるの?経験だけじゃダメ?」
• 「建築一式で出そうとしたら、窓口で断られた」
• 「資料を集めるのが面倒で、つい後回しにしてしまう」
• 「役所に問い合わせたけど、イマイチよく分からない…」
そんな悩みに、建設業許可専門の行政書士として、丁寧に対応します。
こんな方におすすめです
![]() 大阪府・兵庫県で建設業許可を取りたい
大阪府・兵庫県で建設業許可を取りたい
![]() 土日や夜間にも対応してくれる専門家を探している
土日や夜間にも対応してくれる専門家を探している
![]() 「結局、ウチはどうしたらいいの?」をちゃんと教えてほしい
「結局、ウチはどうしたらいいの?」をちゃんと教えてほしい
![]() 許可後の手続き(更新・決算変更届など)も任せたい
許可後の手続き(更新・決算変更届など)も任せたい
相談から許可取得までの流れ
Step 1|まずはお電話をください(相談無料)
土日祝・夜間でも対応しています。
「話を聞いてみたい」だけでもOKです。
Step 2|必要なものをご案内 → お見積り
許可取得の可能性を判断し、必要書類をご案内。
費用も事前に明確にお伝えしますので安心です。
Step 3|書類の作成はお任せください
申請に必要な書類を一式ご用意します。
謄本などの取得もこちらで代行いたします。
Step 4|ご確認・押印 → 当事務所が提出代行
書類は当事務所からお持ちしますので、ご確認・押印をお願いするだけ。
役所への提出もすべてお任せください。
Step 5|申請完了 → 許可取得へ!
申請後、1~2ヶ月程度で許可が交付されます。
よくあるご質問
Q. 何を用意すればいいの?
A. 以下のようなものがあればOKです(ご相談の際に詳しくご案内します)。
• <個人の方> 確定申告書/住民票など
• <法人の方> 履歴事項全部証明書/定款/決算書など
• 経験を証明する書類(請求書・契約書・現場写真など)
• 保有資格の証明書(あれば)
「これで大丈夫かな?」と思ったら、とりあえずバサッと段ボール箱でご用意いただくだけでも構いません。
必要なものはこちらで選別・整理いたします。
当事務所に依頼するメリット
大阪府・兵庫県の建設業許可に精通
![]() 土日祝・夜間も対応可能
土日祝・夜間も対応可能
![]() 決算変更届・更新など、取得後もずっとフォロー
決算変更届・更新など、取得後もずっとフォロー
![]() 宅建業・産廃業など、他の許可との連携もアドバイス
宅建業・産廃業など、他の許可との連携もアドバイス
![]() 登記・税務・社保にも配慮した総合チェック(法律と会計の実務20年以上の実績)
登記・税務・社保にも配慮した総合チェック(法律と会計の実務20年以上の実績)
まずはお気軽にご相談ください(無料)
「うちは許可取れるのかな?」
「何から始めればいいのか分からない」
そんなときは、まずはお電話ください。
「とにかく手続きが苦手」という方も大丈夫!
ゼロから、何度でも、分かりやすくご説明いたします。