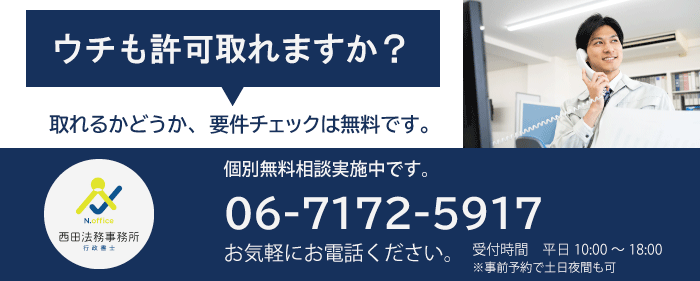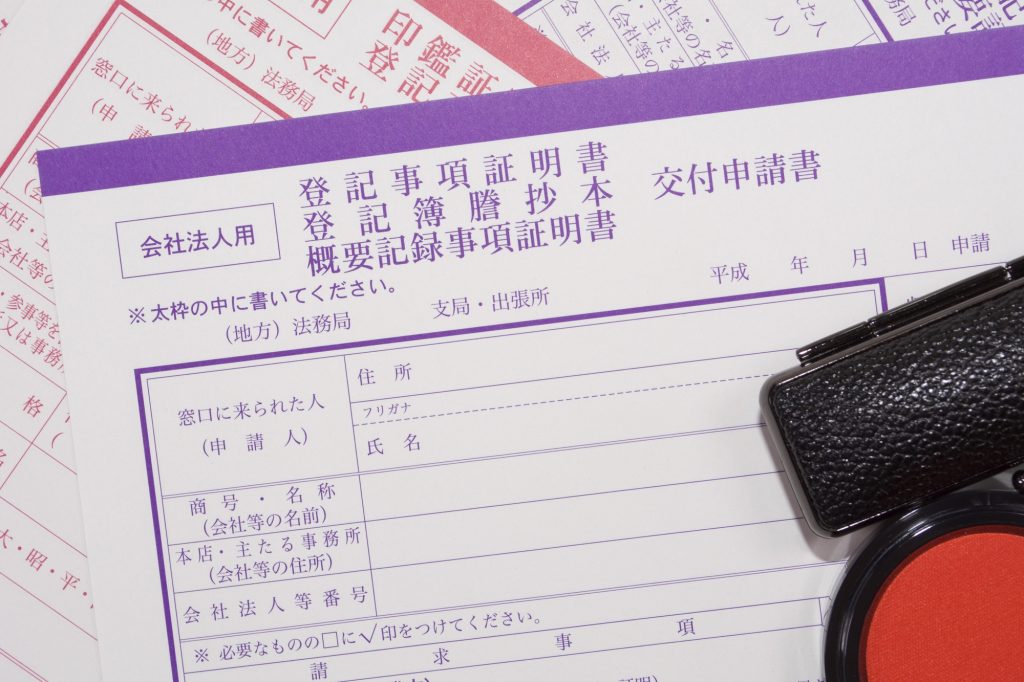
建設業許可の申請に必要な「市町村の長の証明書」や「登記されていないことの証明書」とは
ご相談内容
建設業許可の申請には、「市町村の長の証明書」とか「登記されていないことの証明書」といった書類が必要だと聞きましたが、それが何か分かりません。どんな証明書で、どこで取れるのでしょうか?
元請業者など取引先から
「建設業許可を取ってもらわないと契約できない」
と急に言われたり、
希望する工事を請け負うためには建設業許可の取得が前提条件となっていたりして、
「どうすればいいのか?」
「建設業許可は取れるのだろうか?」と
「建設業の許可を取らないといけないのに、とにかく面倒だし、よく分からない」
このようなご相談をたくさんお寄せいただきます。
みなさんがおっしゃるとおり、建設業許可にまつわる手続きは、なにかと面倒です。
当事務所にご相談をいただくケースでも、
どの書類がいるのか、よく分からない。これでいいの?
と、お困りの方がほとんどです。
そこで、今回は
建設業許可の申請で必要な「市町村の長の証明書」「登記されていないことの証明書」についてご説明させていただきます。
「市町村の長の証明書」とは
市町村の長の証明書とは、
民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書のことをいいます。
この証明書は、本籍地を所管する市区町村窓口で発行されます。
「本籍地」の市役所・区役所なので、「住所地」の市役所・区役所とは異なる場合があるので、取り寄せる際には注意が必要です。
登記されていないことの証明書とは
「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書をいい、
東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の窓口で発行される証明書です。
郵送による交付も可能ですが、郵送の場合は東京法務局のみでしか取り扱っていないので、かえって時間と手間がかかってしまうこともあります。
なお、これら「市区町村長の証明書」や「登記されていないことの証明書」で、成年被後見人・被保佐人である旨が記載されていた場合でも、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨の医師の診断書が提できるのであれば、欠格要件に該当とはなりません。
誰のものが必要なのか
許可を申請する者について必要なのですが、
申請者が法人の場合は、法人の役員全員について必要です。また、支店長など令第3 条に規定する使用人も必要です。
また、いずれも提出前3か月以内のものでなければなりません。