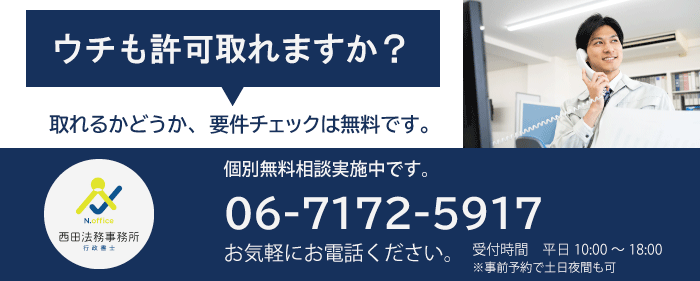大阪・兵庫で建設業許可が必要だけれど「経営経験がないから無理」と思っていませんか?
「建設業許可は取りたいけど、経営経験がない自分でも大丈夫だろうか」
「資格はあるけれど、独立したばかりで申請できるのか不安」
独立したての経営者から、こうしたご相談をいただくことは珍しくありません。
建設業許可は「500万円以上の工事を請け負う場合」に必須ですが、今や金額の大小にかかわらず「許可があるのが当たり前」とされる時代です。
元請や取引先から「許可がないなら仕事を回せない」と告げられることもあり、若手経営者にとっては早急な取得が必須課題になっています。
今回は、建設会社を退職して30代で独立した社長が、役員経験など経営経験がなくても、建設業許可を取得した実例を紹介します。
どんな書類を準備し、どこに注意すればよいのか、実務の流れをわかりやすく解説しています。
相談者のプロフィール
• 年齢・属性:30代前半、元建設会社社員
• 背景:前職では現場監督・現場管理の経験を積み、独立して仲間数人と法人を設立
• 経営業務管理責任者(経管):社長自身は経営経験ゼロ → 要件を満たせない状態
• 専任技術者(専技):本人が2級施工管理技士 → 専技要件はクリア
• 相談動機:独立後すぐに元請から声がかかっており、とにかく最短で許可を取得して受注を逃したくない
初回相談時の課題整理
当初の最大の問題は、経管要件を満たせないことでした。建設業許可を取るためには、原則として「5年以上の経営経験」または「役員経験」が必要です。しかし、社長は独立したばかりで経営経験ゼロ。前職は社員としての現場管理であり、経管の要件に該当しません。
一方で、専技については本人が2級施工管理技士を持っていたため、こちらは要件を問題なくクリアできる状態でした。
つまり課題は「経管をどう確保するか」に絞られました。
建設業許可の要件
一般建設業の許可要件
建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。
①経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)
行政書士の提案と対応策
ヒアリングの結果、最も現実的な解決策は「過去に経管経験を持つ人物を顧問として迎える」ことでした。
具体的には:
• 前職で役員経験のあるOBを経営管理担当役員として迎える
• 会社の登記にも取締役として登記し、入社の手続(社会保険等)を取る
• そのうえで、社長自身は専任技術者として申請
というスキームです。
必要となった書類
今回のケースで準備が必要となった書類は、以下のように整理されました。
経管に関する書類
• 役員として迎える人物の経管経験を証明するための書類
o 前職の会社の建設業許可申請書、許可通知書(経験期間分)
o 社会保険関連の資料
o 商業登記簿謄本(役員としての在籍期間を確認できるもの)
専任技術者に関する書類
• 社長本人の2級施工管理技士の合格証書
• 社会保険に関する資料(常勤であることを確認するため)
その他の法定書類
• 登記事項証明書(会社の謄本)
• 法人事業税の納税証明書
• 決算書類
• 営業所の写真(机・電話・標札等が揃っていることの確認)
• 身分証明書・登記されていないことの証明書(役員全員分) など
証明資料の準備
今回のポイントは、経管として迎え入れる者の証明資料の収集でした。
過去の許可申請書は、元勤務先に協力を依頼する必要があるからです。
さらに、社会保険の手続きにある程度の時間がかかるため、役員就任の登記~社会保険加入手続きまでを担当の社労士さんに無理を言って急ぎの対応をお願いしましたが、気心知れた社労士さんだったので、快く対応していただき、おかげで、この点もスムーズにクリアできました。
行政庁での審査
申請手続きでは、一般的に次のような点を確認していきます。
• 経管となる者の常勤性や経営経験を満たすか
• 社長自身が専任技術者として常勤しているか
• 役員構成に問題はないか
• 営業所の実態(机・電話・標札など)は整っているか
• その他財務要件、など
許可取得の結果とその後
結果として、会社設立から半年足らずのタイミングで、無事に建設業許可を取得することができました。
許可取得後は、元請からの受注もスムーズに進み、500万円を超える工事契約でも問題なく締結できるようになりました。また、許可があることで銀行からの信用も増し、融資やリース契約も有利に進められるようになりました。
この事例のポイント
• 経営経験ゼロでも、他に経管経験者を迎え入れることで解決可能
• 元の勤務先と退職後も良好な関係を保っていたので書類の準備もスムーズにクリアできた
• 早期に行政書士へ相談することで、許可を取得できる可能がみえてくる
今回の30代前半の若手社長の事例では、経営経験ゼロという大きな課題を抱えていましたが、経管経験者を役員として迎えることでスムーズに建設業許可を取得することができました。
建設業許可は「経験や資格がなければ無理」と思われがちですが、情報を整理して、正しい方法と準備をすれば、若手経営者でも十分にクリアできる場合があります。もし同じような状況でお悩みでしたら、まずは一度ご相談ください。
行政書士からのアドバイス
「経営経験がないから建設業許可は取れない」と思っている方は多いですが、今回のように、過去に役員経験のある人物を役員として迎えることで要件を満たせるケースは珍しくありません。
一方で、証明資料の収集や常勤性の確認など、資料の用意や手続きなどで時間を要する場合もあります。大きな仕事が決まってから慌てても間に合わないことが多いため、余裕を持って専門家に相談し、事前に体制を整えておくことが何より重要です。
まずは無料相談で、あなたのケースを確認してみませんか?
許可申請には、要件のチェック・資料の整理など、一定の時間がかかります。
だからこそ、「これからどうすればいいか分からない」と思った段階で一度ご相談いただくことをおすすめしています。
丁寧にヒアリングすることで、
どこまで要件をクリアできているか
どんな書類を用意すればいいか
申請までにどんな準備が必要か
私たちは、こうした点を一緒に整理しながら、現実的な申請の見通しをご提示いたします。
許可が取れるか不安な方へ。
第一歩は、悩みを言葉にすることから
申請はまだ決めていないという方でも、無料相談は歓迎しております。
「もしかしたら自分にもできるかもしれない」
―そんな気づきが、相談の場で生まれることも多くあります。
まずはお気軽にご相談ください(無料)
「うちは許可取れるのかな?」
「何から始めればいいのか分からない」
そんなときは、まずはお電話ください。
「とにかく手続きが苦手」という方も大丈夫!
ゼロから、何度でも、分かりやすくご説明いたします。
「自分のケースだと、どんな感じになるのか知っておきたい」という方へ
建設業許可は、会社のちょっとした変化でも必要な確認事項が変わります。
そこで、
許可が取れるかどうか、
あなたの状況なら、まずここを押さえておくと理解しやすい
というポイントをまとめてみました。
「だいたい、うちの場合はこういう進め方になるのか」
とだいたいの見通しが立てられると思います。
そのうえで、
「もうちょっと詳しく聞いてみたい」
と思われたら、いつでもお気軽にご相談いただけます。
→ 「あなたの状況から分かる建設業許可(カテゴリトップ)」はこちら