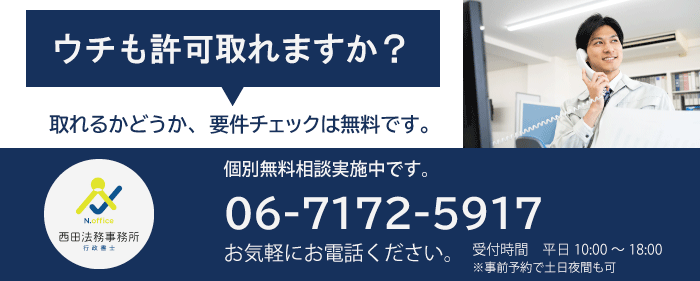申請前に押さえておきたい建設業許可の基礎知識【常勤役員編】
建設業許可を取りたいと考えて調べ始めると、必ず出てくるのが「経営業務の管理責任者」という要件です。
「5年以上の経営経験」と書かれているのを見て、「自分は当てはまるのか?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
建設業を営むには、単に現場の経験や技術力だけでは足りず、経営を適切に管理してきた経験、すなわち「経営経験」を持つ人物が会社にいることが必須とされています。
しかし、この「経営経験」とは一体どのようなものを指すのでしょうか。
- 「現場監督をしていたのだから経営経験に含まれるのでは?」
- 「長年一人親方として工事を請け負ってきたけれど、法人ではないから不安」
- 「自分は長年建設業で働いてきたけれど、経営経験にあたるのだろうか?」
- 「役員として名前は登記されているけれど、実際に経営に携わっていたと認めてもらえるのか?」
実際、この「経営経験5年以上」という要件は、建設業許可を申請する際に最も多くの相談が寄せられるポイントです。
そして、それをどのように「証明できるか」が問われるため、戸惑う方が非常に多いのです。
つまり、「やっていた」ことを裏づける書類が揃わなければ、実際の経験があっても要件を満たしたと認められないのです。
この記事では、特に「常勤役員または個人事業主として5年以上の経営経験を有する場合」という典型的なパターンを取り上げ、
必要となる書類、該当する人のケース、そして実際に認定された事例をわかりやすくご紹介します。
「経営経験5年以上」とは何を指すのか
建設業許可の申請では、法人なら常勤役員、個人事業なら本人または支配人のいずれかが、この「経営経験5年以上」を満たしていれば、経営業務の管理責任者として認められます。
ポイントは、「経営に関与してきた事実を、書類で確認できるかどうか」です。
単に「ずっと会社にいた」「建設業に長く従事している」というだけでは足りません。
証明に必要となるのは次のような書類です。
法人役員の場合
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿)
- 確定申告書や決算書(営業の実態を確認)
- 各年の工事請負契約書や請求書(営業の実績を確認)
個人事業主の場合
- 確定申告書第一表(必要に応じて第二表も)
- 各年の工事契約書や請求書(代表的な工事を証明する)
こういう方が「経営経験5年以上」にあてはまります
では、実際にどんな方がこの要件にあてはまるのでしょうか。
- 法人の取締役として10年以上、会社の経営に関わってきた方
- 一人親方として長年事業を続けてきた個人事業主の方
こうした方は、必要な書類を揃えることで「経営経験5年以上」の要件に合致する可能性が高いといえます。
実際の証明事例
例えば、ある申請では次のように認定されました。
Aさんの場合
- 大阪建設(株)に平成26年4月1日に取締役として就任し、現在まで継続在任。
- 確定申告書(H26.4~R2.3)において役員報酬欄に常勤として記載あり。
- 建設工事の請求書(H26.8~R2.1)が揃っており、12か月以上の空白期間がない。
- 商業登記簿謄本でH26.4から現在までの在任が確認できる。
以上の証拠から期間が全て重なる分(H26.8~R2.1の5年5か月)で役員経験が証明され、
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)として5年以上の経営経験を有することが認められることになります。
行政書士からのアドバイス
 ここで、実際にサポートしていてよく見かけるのが、
ここで、実際にサポートしていてよく見かけるのが、
各年ごとの代表工事を確認しますが、1年以上の空白があったりする場合です。その場合、追加の証明が必要になります。空白がないように、年度ごとの工事記録をしっかり確認しましょう。
また、「名前だけ登記されている」ケースでは認められません。
実際に報酬を得ていたか、契約や経営に関与していたかどうかが重要な判断基準になります。
「経験している」という事実だけでは足りません。
必ず書類で裏づけられることが必要です。これは最も多い勘違いのひとつです。
こうした落とし穴を避けるには、まず 「どの書類で証明できるか」 を把握することが大切です。
・空白期間は要注意
・名義だけの役員では不可
・経験と証明は別物
という点に注意しましょう。
まとめ
「経営経験5年以上」という要件は、一見するとシンプルですが、実際には「経験をどうやって証明するか」が大きなハードルとなります。
・法人役員としての在任記録
・個人事業主としての確定申告書
・工事契約書や請求書などの営業実績
これらを整理し、矛盾や空白のない形で提出することが、建設業許可取得のカギです。
「自分の経歴で本当に大丈夫なのか?」
「必要な書類が揃っているのか心配だ」
そう感じる方は、専門家に相談するのが一番確実です。
大阪・兵庫での申請サポート経験が豊富な当事務所では、要件確認から書類の準備、提出まで一貫してサポートしています。
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。