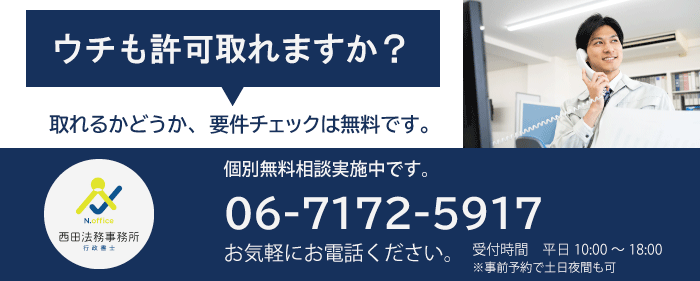取引先から「法人でないと契約できない」と言われたら?―法人化と許可申請の進め方
「元請から法人でないと契約できないと言われてしまった」
地元で一人親方としてこれまで問題なく工事を続けてきたけれど、
新しい取引先との契約にあたり、法人化を求められご相談にこられるケースもよくあります。
法人化と同時に建設業許可も取ることができれば、
元請からの信頼が高まり、より大きな案件や安定した仕事を受けられるようになります。
今回は、40代前半の内装工事業の職人社長さんが、法人化と同時に建設業許可を取ろうとされたケースをもとに、
会社設立の具体的な流れや許可取得の要件、実務経験とはどういうものなのか考え方を整理して解説します。
法人化を検討している方にとって参考になるかと思います。
一人親方が法人化と同時に建設業許可を取りたいという場合
内装工事業・40代前半の職人社長のケース
地元で一人親方として内装工事を10年以上続けてきた四十代前半の職人社長。
更なる業績アップにつながりそうな、ある取引先を紹介してもらいましたが、その取引先企業から「法人でないと契約できない」と言われ、法人化を決意しました。
これをきっかけに、法人化と同時に建設業許可も取得し、これまで以上に幅広く仕事を受けられるようにしたいということでご相談にこられました。
社長ご本人には個人事業主として10年以上の経営経験があり、経営業務管理責任者(経管)の要件は社長ご自身で満たせる見込みがありましたが、一方で、専任技術者(専技)となるために必要な国家資格等はお持ちではいませんでした。
そのため社長ご自身は「実務経験でいけると聞いたが、自分は大丈夫なのか」との不安を抱えていらっしゃいました。
そこで、法人化の準備と並行して、この専技の要件をどのように整理していくのかがひとつの大きなポイントでした。
法人化を先に進める
建設業許可を申請する際には、法人の内容に基づいて申請書や添付書類を作成することになります。
つまり、商号や本店所在地、役員構成といった基本的な事項が確定していなければ、許可申請を進めることができません。
そのため、まずは法人化を早急に完了させることが、許可取得への第一歩となります。
会社の形態については株式会社か合同会社かを選ぶことになります。
株式会社は公証役場での定款認証が必要で、信用度を重視する場合や将来の資本政策を見据える場合に選ばれることが多い形態です。
一方、合同会社は定款認証が不要で、設立手続きもシンプルです。
いずれを選んでも建設業許可の申請するうえでは差はありませんので、自社の経営方針に合わせた形態を選ぶのがよいでしょう。
また、定款の事業目的には必ず「内装仕上工事業」といった文言を明確に入れておく必要があります。
ここが不明確だと、審査の時に「建設業者としての目的に該当しないのでは」と判断されることもあり得ます。
さらに、法人化にあわせて、営業所の実態を整えることも重要です。
机や電話、看板などの備えがあり、建設業を営む事務所としての態勢をきちんと整えておく必要があります。
建設業許可の準備も同時進行で
実務的には、法人登記が完了してから建設業許可を申請する流れとなります。
ただ、登記の手続きと並行して、許可申請に必要な要件確認や書類収集を進めておくようにします。
これにより、登記完了後すぐに許可申請に移行でき、法人化と許可取得をスムーズにつなげることができます。
建設業許可に必要な要件
建設業許可を得るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
一般建設業の許可要件
建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。
①経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)
専任技術者は実務経験で申請
所定の国家資格等がない場合、専任技術者の要件を満たす方法として、「実務経験」が認められています。これは、定められた実務経験証明書を作成し、その裏付けとなる工事の実績など確認書類を提出することで行います。
実務経験を裏付ける資料として、その工事が行われたことを示す契約書や注文書・請書、請求書などの書類が必要です。ここで大切なのは、内装仕上工事業の業種で申請するので、実務経験となるその工事が「内装仕上」であることが明確にわかるものでなければなりません。工事名や内容が漠然・曖昧としているものでは工事の実績として認められないため、工事の内容や工期、請負金額などが明確に確認できる資料をきちんと残しておくことが重要です。
経営業務の管理責任者の確認
経営業務の管理責任者については、社長本人が個人事業主として10年以上の経営経験を積んできたため、これを根拠として申請します。それを裏付けるものとして、確定申告書や工事契約書など経営が実際に継続して行われていたことが必要となります。
財務要件・営業所要件・社会保険関連の準備
建設業許可を受けるためには、財務面や社会保険でも一定の基準を満たしていなければなりません。具体的には、500万円以上の資金がある(一般許可の場合)など資金力を示す資料を整えることが求められます。また、営業所については、単なる登記上の所在地だけでなく、実際に業務を行える事務所が存在することが確認できる資料が必要です。
さらに、社会保険や雇用保険についても、法人として加入手続きを済ませていることが必要です。これらは設立後の届け出とあわせて社労士さんに確実に対応してもらいました。
申請の流れ
まとめると、実務の流れは次のようになります。
まず法人の基本事項を決定し、株式会社なら定款を公証役場で認証したうえで、法務局で設立登記を行います。
登記が完了したら、税務署や県税事務所などへの届出、社会保険や労働保険の手続きを済ませます。
この間に、建設業許可申請に必要な要件の最終確認を行い、申請書や様式の作成を進めます。工事の実績確認書類を整理し、申請書類として仕上げます。
そして設立登記やその他社会保険関連の手続きが完了したら、建設業許可の申請窓口へ提出して審査を受ける流れとなります。
法人化と許可申請を「別々に」進めるのではなく、できる限り「並行して」準備することで、法人化と同時にスムーズに許可を取得できるようになります。
行政書士からのアドバイス
今回のケースは、長年一人親方として仕事をしてきた職人社長が、法人化を機に建設業許可取得を目指すというものでした。
経営経験は十分にあるため経管の要件は満たせますが、専任技術者は資格がなく、実務経験で証明する必要がありました。
この場合、各年の代表工事を裏付ける契約書や請求書を提出することが必要です。
法人化は許可取得のための前提であり、会社の形態や目的、営業所の実態、役員体制を整えることが不可欠です。
そして、許可の要件を一つひとつ確実にクリアしていくことが、法人化と同時に許可を得るためのポイントになります。
資格がなくても、実務経験を積み上げ、きちんと書類を整えていれば十分道は開けます。
大切なのは、不安を抱えたままにせず、早めに準備に着手し、確実に進めることです。
まずは無料相談で、あなたのケースを確認してみませんか?
許可申請には、要件のチェック・資料の整理など、一定の時間がかかります。
だからこそ、「これからどうすればいいか分からない」と思った段階で一度ご相談いただくことをおすすめしています。
丁寧にヒアリングすることで、
どこまで要件をクリアできているか
どんな書類を用意すればいいか
申請までにどんな準備が必要か
私たちは、こうした点を一緒に整理しながら、現実的な申請の見通しをご提示いたします。
許可が取れるか不安な方へ。
第一歩は、悩みを言葉にすることから
申請はまだ決めていないという方でも、無料相談は歓迎しております。
「もしかしたら自分にもできるかもしれない」
―そんな気づきが、相談の場で生まれることも多くあります。
まずはお気軽にご相談ください(無料)
「うちは許可取れるのかな?」
「何から始めればいいのか分からない」
そんなときは、まずはお電話ください。
「とにかく手続きが苦手」という方も大丈夫!
ゼロから、何度でも、分かりやすくご説明いたします。
「自分のケースだと、どんな感じになるのか知っておきたい」という方へ
建設業許可は、会社のちょっとした変化でも必要な確認事項が変わります。
そこで、
許可が取れるかどうか、
あなたの状況なら、まずここを押さえておくと理解しやすい
というポイントをまとめてみました。
「だいたい、うちの場合はこういう進め方になるのか」
とだいたいの見通しが立てられると思います。
そのうえで、
「もうちょっと詳しく聞いてみたい」
と思われたら、いつでもお気軽にご相談いただけます。
→ 「あなたの状況から分かる建設業許可(カテゴリトップ)」はこちら