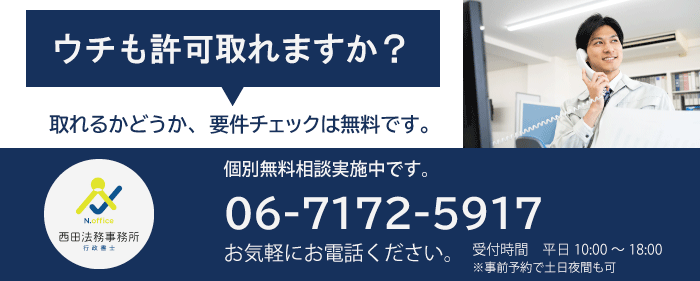建設業免許(許可)取得の要件と手続きの流れ|初めての方必見
「何から始めればいいかわからない。」
「自分で調べてみたけど、結局よく分からなくて…。」
建設業許可のご相談をいただく中で、特に多いのがこのようなお声です。
- 「個人事業のときの経験って、カウントされるの?」
- 「確定申告書はあるけど、年数が足りているか不安…」
- 「自分が経営責任者と技術者、両方できるんでしょうか?」
許可申請には、要件・書類・経歴の確認など、いくつものハードルがあり、初めての方にはかなり複雑に感じられます。
ネットの情報を調べてみても、自分のケースがどこに当てはまるのか分からず、手が止まってしまう…そんな方が実際に多くいらっしゃいます。
でも、 そんなときにこそ、遠慮せず、無料相談をご活用いただきたと思います。
今回は、神戸市で内装工事業を営む40代の法人代表の方のケースをご紹介します。
この方も、最初はおひとりで悩んでいらっしゃいましたが、
ふと思い立って当事務所へ無料相談をされたことがきっかけで許可の取得まで進んだというケースです。
【事例紹介】書類を整理したら、申請の道筋が見えた
「元請けから『そろそろ許可を取ってくれないか』と言われて焦って調べ始めたものの、条件に合っているのか全く分からなくて…」
と、ご相談に来られました。
この方のように、法人化して間もない場合、
「実績が足りないのでは」
「今申請しても無理かも」
と不安を感じられることが多いです。
建設業許可とは
一般建設業の許可要件
建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。
①経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)
「①経営業務の管理責任者を有すること」とは
経営業務の管理責任者とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する人のことをいいます。 法人では常勤の「役員」、個人では「事業主か、支配人」となっている人でなければなりません。 そして、この「経験」とは、主に、建設業に関して5年以上の経営経験があることが必要です(他にもいろいろあります)。
「②営業所ごとに置く専任技術者を有すること」とは
専任技術者とは、所定の国家資格や、所定学科を卒業した人などのことをいいます。 簡単に言うと、一定の技術レベルを持った人を技術面での責任者として常駐させないとダメですよということです。なおかつ、その人は、自社に「専任」かつ「常勤」で勤務している人でなければなりません。
「③誠実性を有すること」とは
申請人である会社やその役員、事業主である本人などが、請負契約に関して「不正または不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことをいいます。不正行為とは、請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律行為を指し、不誠実な行為とは、工事の内容、工期などに関する請負契約違反をいいます。
「④財産的基礎または金銭的信用を有すること」とは
申請する日の直前の決算において、自己資本額が500万円以上であるか、または500万円以上の資金調達が可能であるか、あるいは申請時点で5年以上許可を得て営業しているかのうちどれか1つを満たしていることが必要です。
「⑤欠格要件に該当しないこと」とは
次のいずれにも該当しないことをいいます。
・申請書類に、虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けていたりしないこと
・法人ではその法人の役員、個人ではその本人などが、 成年被後見人や破産者でまだ復権を得ていないとか、一定の刑罰を受けたことがあるとか、過去に許可の取り消しを受けたことがあるとか、所定のペナルティを受けたりしていないこと。
以上のような要件をすべて満たしていれば許可が取得できます。
このケースの場合
実際に確認したところ…
・個人事業主としての確定申告書が6年分保管されていた
・工事台帳や見積書など、技術者としての業務内容を示す資料が時系列で残っていた
・法人化して2年が経過しており、経営業務の経験年数と通算できる可能性があった
これらの事実をもとに、個人事業時代の経験+法人代表としての経歴で条件を満たせると判断できました。
ご本人は当初「足りてないと思っていた」とおっしゃっていましたが、きちんと整理し、実態を説明できる形に整えることで、許可取得に必要な要件をクリアしていたのです。
「相談したからこそ見えたこと」がある
要件に当てはめるのが難しい。
条件を満たすかどうかは奥が深い。
理屈は分かっても、じゃあ実際自分はどうなんだとなると、それがいちばんよく分からないところだったります。
建設業の許可の申請は、ボリュームもあって、しかも細かいです。
正直なところ、上記に述べた要件に杓子定規に当てはめてみても、取れるかどうかなんて判断できません。
様々な資料や会社の状態、従業員や取引の状況など、あらゆる情報を総合して判断するものです。
資格がないから取れないとは限らないし、
でも、10年以上経験してきたからといってそれで問題ないかといえばそうでもない。
経歴ひとつとっても、単純にはいかないことが多いです。
また「税金対策は税理士とちゃんと話ができているから問題ない」と安心して
税金対策ばかりに捉われていて建設業許可が取れなくなってしまうというケースも多いです。
ご自身だけでは「ムリだろう」と諦めていた方でも、専門家の視点で確認することで、進められる根拠が見つかることは少なくありません。
まずは無料相談で、あなたのケースを確認してみませんか?
許可申請には、要件のチェック・資料の整理など、一定の時間がかかります。
だからこそ、「これからどうすればいいか分からない」と思った段階で一度ご相談いただくことをおすすめしています。
丁寧にヒアリングすることで、
どこまで要件をクリアできているか
どんな書類を用意すればいいか
申請までにどんな準備が必要か
私たちは、こうした点を一緒に整理しながら、現実的な申請の見通しをご提示いたします。
許可が取れるか不安な方へ。
第一歩は、悩みを言葉にすることから
申請はまだ決めていないという方でも、無料相談は歓迎しております。
「もしかしたら自分にもできるかもしれない」
――そんな気づきが、相談の場で生まれることも多くあります。
建設業許可のこと、相談してみませんか?

「許可が必要って言われたけど、何から始めたらいいのか…」
「書類が多すぎて手が止まっている…」
そんなときは、一度ご相談ください。
大阪府・兵庫県の建設業許可に詳しい当事務所が、あなたの申請をしっかりサポートいたします。
よくあるご相談
建設業許可の申請には、意外と多くの落とし穴があります。
当事務所に寄せられるご相談の一例をご紹介します。
• 「資格がいるの?経験だけじゃダメ?」
• 「建築一式で出そうとしたら、窓口で断られた」
• 「資料を集めるのが面倒で、つい後回しにしてしまう」
• 「役所に問い合わせたけど、イマイチよく分からない…」
そんな悩みに、建設業許可専門の行政書士として、丁寧に対応します。
こんな方におすすめです
![]() 兵庫県で建設業許可を取りたい
兵庫県で建設業許可を取りたい
![]() 土日や夜間にも対応してくれる専門家を探している
土日や夜間にも対応してくれる専門家を探している
![]() 「結局、ウチはどうしたらいいの?」をちゃんと教えてほしい
「結局、ウチはどうしたらいいの?」をちゃんと教えてほしい
![]() 許可後の手続き(更新・決算変更届など)も任せたい
許可後の手続き(更新・決算変更届など)も任せたい
相談から許可取得までの流れ
Step 1|まずはお電話をください(相談無料)
土日祝・夜間でも対応しています。
「話を聞いてみたい」だけでもOKです。
Step 2|必要なものをご案内 → お見積り
許可取得の可能性を判断し、必要書類をご案内。
費用も事前に明確にお伝えしますので安心です。
Step 3|書類の作成はお任せください
申請に必要な書類を一式ご用意します。
謄本などの取得もこちらで代行いたします。
Step 4|ご確認・押印 → 当事務所が提出代行
書類は当事務所からお持ちしますので、ご確認・押印をお願いするだけ。
役所への提出もすべてお任せください。
Step 5|申請完了 → 許可取得へ!
申請後、1~2ヶ月程度で許可が交付されます。
よくあるご質問
Q. 何を用意すればいいの?
A. 以下のようなものがあればOKです(ご相談の際に詳しくご案内します)。
• <個人の方> 確定申告書/住民票など
• <法人の方> 履歴事項全部証明書/定款/決算書など
• 経験を証明する書類(請求書・契約書・現場写真など)
• 保有資格の証明書(あれば)
「これで大丈夫かな?」と思ったら、とりあえずバサッと段ボール箱でご用意いただくだけでも構いません。
必要なものはこちらで選別・整理いたします。
当事務所に依頼するメリット
大阪府・兵庫県の建設業許可に精通
![]() 土日祝・夜間も対応可能
土日祝・夜間も対応可能
![]() 決算変更届・更新など、取得後もずっとフォロー
決算変更届・更新など、取得後もずっとフォロー
![]() 宅建業・産廃業など、他の許可との連携もアドバイス
宅建業・産廃業など、他の許可との連携もアドバイス
![]() 登記・税務・社保にも配慮した総合チェック(法律と会計の実務20年以上の実績)
登記・税務・社保にも配慮した総合チェック(法律と会計の実務20年以上の実績)
まずはお気軽にご相談ください(無料)
「うちは許可取れるのかな?」
「何から始めればいいのか分からない」
そんなときは、まずはお電話ください。
「とにかく手続きが苦手」という方も大丈夫!
ゼロから、何度でも、分かりやすくご説明いたします。