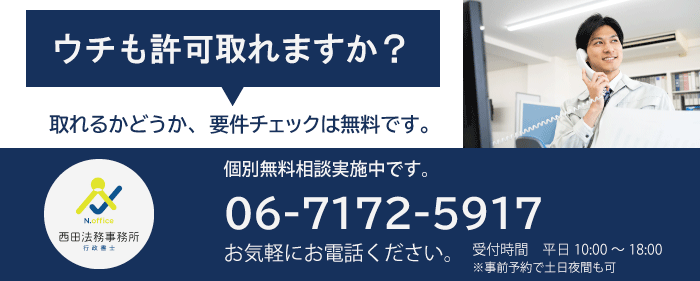現社長が勇退して、後継者に任せたいというときの落とし穴
社長の代替わり。
このとき、うっかりやってしまって取り返しがつかなくなることがあるということを
ご存知ですか?
相続対策だといって簡単に代替わりしてしまう。
これは、最も多い間違いのひとつです。
建設業許可を維持していくために必要なこと
「社長を息子と代わった」と簡単におっしゃる方が多いですが、
建設業許可を受ける条件のひとつに、
「経営管理の責任者がいること」
というのがあります。
社長さん自らがその経営管理責任者として建設業許可を取得されている会社さんは多いですが、
そのパターンの方は要注意です。
たとえば、息子さんを会社に招き入れ、
めでたく息子さんを社長に就任させるというケースは普通によくある話なのですが、
ここで、
許可を維持していくための要件として、
その息子さんに、少なくとも5年以上の役員経験がないといけません。
ですので、現社長が引退するというその頃になって役員に就任しても遅すぎるわけです。
なのに、うっかり、現社長が代表取締役を退任なんてしてしまうと、
経営管理責任者がいなくなった状態となってしまい、
許可の要件を満たさないということになり、建設業許可は取り消しになってしまいます。
「だったら、すぐ誰か代わりを用意すればいいのでは?」
というふうにお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そう甘くはありません。
たった「1日」でも空白期間を作ってしまうとアウトです。
たった1日でも建設業許可基準を満たさない時間ができてしまうと、取消し処分の対象となる場合があります。
実際にご相談いただいたケース
| 兵庫県神戸市 H社様(総合建設業) |
|---|
| 建築一式業 とび土工業 内装仕上工事業 ほか
役員:代表取締役(現社長) H様 |
この会社様は、もともと建設業許可を持っていらっしゃった会社で、
このときは全く別の手続きのことでご相談を受けていました。
たまたま息子さんの話になり、
「今度、社長を息子に譲って自分は引退するんだけど、何か手続きいる?」
という話になりました。
幸いまだ実際に引退されたわけではなかったので、とにかくストップをかけて、
ひとまず状況を整理しました。
息子さんは同じ会社ですでに取締役のポストについておられましたが、
登記を確認すると、就任してからまだ3年と数カ月しか経っていませんでした。
私はあわてて、状況を説明し、
「まだ引退してはいけません。あと2年ガマンして下さい!」と申し上げました。
経営管理責任者を交代させるには
建設業許可の要件
建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。
①経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)
「①経営業務の管理責任者を有すること」とは
経営業務の管理責任者とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する人のことをいいます。 法人では常勤の「役員」、個人では「事業主か、支配人」となっている人でなければなりません。 そして、この「経験」とは、主に、建設業に関して5年以上の経営経験があることが必要です。
イ 常勤役員等のうち一人が次の( a1)(a2)(a3)いずれかに該当する者であること
(a1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(a2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(a3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
(他にもいろいろあります)。
しかも、常勤でなければなりません。
常勤とは?
早い話が、フルタイム勤務ってことなんですが、正確には、
本社・本店において、休日などを除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者で、かつ、報酬が一定の額以上ある者、をいいます。
けっきょくこのケースではどうしたのか
このケースでの会社さんは、
それから、社長さんが関係各所といろいろと調整を重ねた結果、息子さんの取締役就任から5年を経過するまでは現役を続行することになりました。
それから3年ほど社長さんは会社に残り、無事に代替わりして今では会長職に就かれ、悠々自適なセカンドライフを謳歌されていらっしゃいます。
行政書士からのアドバイス
節税対策には気を付けていらっしゃる経営者さまは多くいらっしゃいますが、
特に、生命保険を使った退職金のスキームを組まれている方は、お気を付け下さい。
多くの場合は、税理士さんのアドバイスをもとに
保険会社さんにスキームを組んでもらっていると思いますが、
私の経験では、建設業許可のことまで踏まえてスキームを組んでおられた方は、ひとりもいらっしゃいませんでした。
ほかの業界の会社なら、これらは大した問題ではありません。
でも建設業者にとっては、ひとつ間違えると、退職金が出せないなんてことにもなりかねません。
そうすると会社の納税にも大きく影響します。
「いや~うっかりしてました。すぐ訂正しますんで。」なんて言い逃れは一切認めてもらえません。
特にご注意ください。
当事務所は、建設業許可の手続を専門とした申請代行業務をおこなっております。

- 兵庫県の建設業許可に詳しい専門家をお探しの方
- 日中は忙しいので、土日や夜間でも対応してくれるところをお探しの方
- 丁寧に分かりやすく説明してくれるところをご希望の方
建設業許可のこと、当事務所に相談してみませんか?
分からないことがあれば、とりあえず聞いてみるのがいちばんです。
「書類とか手続きとか、とにかく苦手。もう、なんのことやら、さっぱり分からない。」
そのような方でも、ご安心下さい。
ゼロから、何度でも、ご説明させていただきます。
「許可を取得して以来、何もメンテナンスしていないな…。」
と思われたら、いちどご相談下さい。
見落としている手続きがないかなど、無料でチェックさせていただきます。
建設業許可は、建設業者様にとっては、お仕事に大きく関わる 会社の重要な資産 です。
建設業許可も、きちんと定期的なメンテナンスを入れてみてはいかがでしょうか?
当事務所では、お客様のお話をじっくりとお聞きして、
お客様にとってのベストな解決策をご提案いたします!
建設業許可のことでお困りのときは、
どうぞお気軽にお電話ください。