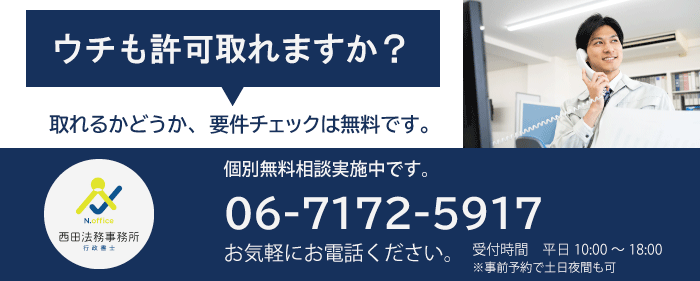建設業の許可を取りたいのですが、
「建築一式工事業」というものを取っておけば、すべての工事ができるのではないのですか?
建設業許可を取りたいという方からのご相談で、このようなご質問をうけることがあります。
建設業許可を調べてみると「建築一式工事業」という言葉が目に入ります。
名前から受ける印象もあってか、
「とりあえず、この『建築一式』の許可を取っておけば、どんな工事でも請け負えるのではないか」
と考える方が非常に多いのが実情です。
実際、相談を受ける場面でも、「一式で取れば大丈夫なんですよね?」という質問は少なくありません。
しかし、これは大きな誤解です。
建設業許可は29の業種に分かれており、「建築一式工事業」はあくまでも一つの業種に過ぎません。
しかも、この「一式工事業」には明確な定義と適用範囲があって、全ての建築関連工事をカバーできるという意味では使われていません。
例えば、外壁塗装や内装仕上げといった工事はそれぞれの業種の許可がなければ単独で請け負うことはできず、建築一式業の許可でカバーできるのではありません。
「建築一式工事業」とは、複数の専門工事を総合的に取りまとめて一つの建築物を完成させるような、規模が大きく複雑な工事に対して適用されるものです。
住宅の新築一棟や増改築、ビルやマンションの大規模修繕といった工事がその典型です。
一方で、水回りリフォームや壁紙の張り替えなど、比較的小規模で単独の工種で完結する工事は、一式工事には含まれません。
「とりあえず建築一式で許可を取っておこう」と安易に考えると、実際の工事内容との不一致が生じ、あとになって「必要な許可が取れていない」という事態になりかねません。
しかも、一度許可を取得したあとで業種を変更することは、実務上かなり難しいのが現実です。
特に資格者を持たずに実務経験で要件を満たそうとする場合、要件を再度積み直す必要が出るため、「あとで変えればいい」という発想は非常に危険です。
この記事では、建設業許可における「建築一式工事業」とはどういうものか、そして「何でもできる許可ではない」という点を中心に解説します。これから許可申請を検討している方にとって、「自社の工事に合った業種を正しく選ぶこと」がいかに大切かを理解するきっかけになれば幸いです。
建設業許可の「業種」とは
建設業の許可には種類があって、29種類に分かれています。
これを「業種」と呼んでいます。
「業種」について詳しくはこちらをご覧ください。
建設業許可の「業種」は、まず大きく「一式工事」と「専門工事」に分けることができます。
一式工事と専門工事の違い
建設業の許可は、2つの一式工事と27の専門工事に分かれていて、その会社の仕事内容に対応した許可の業種を選ばないといけません。
どの種類の許可が必要になってくるのか?それは、請負契約の内容により判断されます。
許可を必要としない「軽微な建設工事」を除いて、個別の専門工事の請負であれば、その工事に対応する専門工事の許可が必要であり、一式工事の許可では請け負うことはできません。
ご自身のお仕事が、どの種類にあてはまるのか、どのような工事を請け負えるかについて、普段請け負っているお仕事の契約内容をよく見て、判断しなければなりません。
「一式工事」とはどんな許可なのか
一式工事は、「総合的な企画、指導および調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事」のことをいいます。
典型的なのは、住宅建築でいえば「新築一棟」の工事です。
ですので、水廻りだけのリフォームでは一式工事とはいえません。
リフォーム工事なら、いわゆる「フルリフォーム」とか「リノベーション」といわれるような、大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事など、複数の専門工事の組み合わせで構成されるようなものを指します。
とはいえ、単一の専門工事であっても、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものになると、一式工事として扱うとされています。
けっきょくのところ、その工事の契約内容からして、大規模だったり、施工が複雑な工事だったりで、複数の建設業者が関わるような工事で、ご自身の会社が元請けとして、総合的に全体を取り仕切っていくこと(マネジメントしていくこと)が必要です。
なので、一式工事は、原則として「元請け」として工事を請け負うことが大前提です。下請業者が、元請業者から一式工事を請け負うということは、ありえません。そもそも法律で定められている「一括下請負の禁止」に反する可能性があるため、やってはいけないものです。
専門工事とは
一方、専門工事は、27種類に分かれています。
どの種類にあてはまるのか、その判断が微妙な場合はたくさんあります。
一概にコレとは、なかなか言えません。もう「ケースバイケースです」としか言いようがないくらいです。
これもやっぱり、請負契約の内容により判断されます。
なお、一式工事を請け負った場合には、通常、一式工事の内容に個別の専門工事が含まれている感じになりますが、実際にその施工にあたる場合は、それぞれの専門工事に対応した技術者の配置が必要となります。
「一式工事業」の許可なら何でもできる、は大間違い?
一式工事はオールマイティな許可業種ではありません。
建設業許可の種類のうち、土木一式工事・建築一式工事という「一式工事」と呼ばれるものと、「専門工事」と呼ばれる「塗装工事」や「解体工事」など27種類の業種は、まったく別の許可業種です。
上の例だと、外壁塗装工事で500万円以上の工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可(この場合なら「塗装工事業」の許可)がなければ請け負うことはできません。
他にも、例えば、住宅の壁紙を貼る工事を請け負った場合、新築工事の現場でのお仕事だと建築一式の工事に思えそうなのですが、あくまで「内装仕上工事」であって、建築一式工事の許可ではありません。
建築一式工事にあたるもの
一般的に下記のような工事が建築一式工事と判断されます。
- 複数の専門工事(大工工事、屋根工事、とび·土工工事、建具工事、電気工事、内装仕上工事、塗装工事、管工事など)を有機的に組み合わせた1つの建築工事
- 住宅等の新築工事·増改築工事、ビル等大規模な建築物の解体工事、マンションの大規模修繕(補修)、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事など。
- 建物の躯体(柱、梁などの建物本体の構造を支える部分)に変更を加える改造工事
- 耐震補強工事、大規模な模様替など
※一般的に建築確認申請の対象となるような工事が建築一式工事に該当するといわれています。
※一般的な住宅リフォーム工事は、通常内装仕上工事が主たる工事と認められるケースが多く、この場合は原則として専門工事と判断されるが、増改築を伴う大規模・複雑な場合は、建築一式工事に該当する。
土木一式工事にあたるもの
- 道路工事、橋梁工事、河川工事・海岸工事、
- トンネル工事、ダム工事、
- 大規模な宅地造成工事(とび・土工で施工困難な工事)など
- プレストレストコンクリート工事、
- 下水道工事(公道下等の下水道の配管工事)、下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事
※下請工事は原則専門工事となる。
「とりあえず取っておいて、あとで変更すればいい」という考えは危険です。
建設業許可のご相談を受ける中で
「『一式工事』ってやつを取っておけば、何でもいけるんですよね?」
というご質問はものすごく多いです。
バッサリ言ってしまうと、それは勘違いです。
例えば、実際に普段請け負っているお仕事が外壁塗装工事なのに、一式工事の許可さえあれば大丈夫などと考えて、それで取ってしまうと後で大変なことになりかねません。
「あとで変更すればいいんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、そうもいかないことが多いんです。
国家資格等をお持ちの方ならまだしも、
実務経験で許可を取ろうとお考えなら、なおさらここの話は慎重に進めていかないと、あとで変更するということが、ほぼ無理だと言っていいでしょう。
まずは無料相談で、あなたのケースを確認してみませんか?
許可申請には、要件のチェック・資料の整理など、一定の時間がかかります。
だからこそ、「これからどうすればいいか分からない」と思った段階で一度ご相談いただくことをおすすめしています。
丁寧にヒアリングすることで、
どこまで要件をクリアできているか
どんな書類を用意すればいいか
申請までにどんな準備が必要か
私たちは、こうした点を一緒に整理しながら、現実的な申請の見通しをご提示いたします。
許可が取れるか不安な方へ。
第一歩は、悩みを言葉にすることから
申請はまだ決めていないという方でも、無料相談は歓迎しております。
「もしかしたら自分にもできるかもしれない」
――そんな気づきが、相談の場で生まれることも多くあります。
![]() 「一人親方だけどウチの会社でも許可って取れるの?
「一人親方だけどウチの会社でも許可って取れるの?
![]() 「役所に相談に行ったけど、結局よく分からなかった」
「役所に相談に行ったけど、結局よく分からなかった」
![]() 「専門家に相談と言われても、顧問の税理士さんしか知らない」
「専門家に相談と言われても、顧問の税理士さんしか知らない」
建設業許可の手続きに詳しい行政書士がサポートいたします。
日中お忙しい方は夜間や土日に診断もできますので、電話・メールにてご予約ください。

まずはお気軽にご相談ください(無料)
「うちは許可取れるのかな?」
「何から始めればいいのか分からない」
そんなときは、まずはお電話ください。
「とにかく手続きが苦手」という方も大丈夫!
ゼロから、何度でも、分かりやすくご説明いたします。
取引先から「建設業許可を取ってください」と言われた方へ
取引先から急に許可を求められたときに、
「なぜ必要なのか」
「自分は取れるのか」
「何から始めればよいのか」
を分かりやすく整理していますのでチェックしてみて下さい。
→ 「取引先に建設業許可を求められたら読むページ(カテゴリトップ)」はこちら